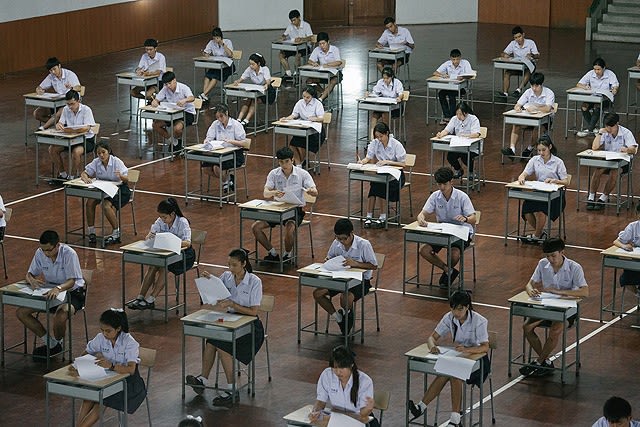映画「きみの鳥はうたえる」を映画館で観てきました。
![]()
函館出身の作家佐藤泰志の芥川賞候補作品「きみの鳥はうたえる」の映画化である。原作は未読。海炭市叙景、そこのみにて光輝く、オーバー・フェンスと佐藤泰志原作の映画化作品はいずれも傑作であった。函館の町を舞台に社会の底辺をさまよう人たちに存在感を持たせる。今回も期待して映画館に向かう。
結果としては、前の3作ほど良くはなかった。でも、この映画でも若い3人の若者が函館の街に放たれている。寂れつつも独特の存在感を持つ函館の街の匂いが映画全面に漂う。クラブやビリヤード場の映像は今までの作品になかったところ、猥雑で喧噪な若者のたまり場に流れる雰囲気はいい感じだ。函館山や路面電車を3人のバックの映像にチラチラ登場させるのを見ると、直近に三度函館で遊んだ自分はなんかわくわくしてしまう。
調べると、この題ってビートルズの「And your bird can sing 」の日本語訳ですってね。アルバム「リヴォルバー」の中にあるジョン・レノンの曲、ジョンとジョージのツインギターで軽快に始まるジョン・レノンのヴォーカルが印象的な自分の好きな曲だけど、映画の中じゃ全然流れなかったなあ。全く気づかなかった。
函館郊外の書店で働く「僕」(柄本佑)は、失業中の静雄(染谷将太)と小さなアパートで共同生活を送っていた。ある日、「僕」は同じ書店で働く佐知子(石橋静河)とふとしたきっかけで関係をもつ。彼女は店長の島田(萩原聖人)とも抜き差しならない関係にあるようだが、その日から、毎晩のようにアパートへ遊びに来るようになる。こうして、「僕」、佐知子、静雄の気ままな生活が始まった。
![]()
夏の間、3人は、毎晩のように酒を飲み、クラブへ出かけ、ビリヤードをする。佐知子と恋人同士のようにふるまいながら、お互いを束縛せず、静雄とふたりで出かけることを勧める「僕」。
そんなひと夏が終わろうとしている頃、みんなでキャンプに行くことを提案する静雄。しかし「僕」は、その誘いを断り、キャンプには静雄と佐知子のふたりで行くことになる。次第に気持ちが近づく静雄と佐知子。函館でじっと暑さに耐える「僕」。3人の幸福な日々も終わりの気配を見せていた……。 (作品情報引用)
![]()
アパートで同居する男2人に女の子が絡まる函館が舞台の青春映画、僕と佐知子が何気ないきっかけでぐっと近づいていく。2人が働く本屋の店長と付き合っていたのに、佐知子は気がつくと若い僕との付き合いが楽しくなる。僕の同居人の静雄も加えて夜通し遊んでいくうちに静雄にも情が移る。三角関係になるわけだ。でも、激しい葛藤があるわけではない。淡々とストーリーが流れる。起伏の少なさが若干物足りない。
石橋静河がいい。石橋凌と原田美枝子の娘と聞くと驚くが、何となく面影はある。かわいい。ここでは柄本佑と軽い絡みを見せるが、バストトップは見せない。若くして大胆に脱いだお母さんとは違うなあ。母娘バストの形は似るというが、24歳だからかまだ出し惜しみだ。
![]()
クラブのシーンでは、ソロで踊ったりする。うまいというわけではないが、まあ味のあるダンスを踊っていると思ってプロフィルを見たら、一応はダンサーという肩書きもあるんだね。萩原聖人演じる中年の店長と不倫関係にあるという設定だけど、不自然さがない。大人びている。親も親なんでませた人生送ってきたんだろう。この若い2人がともに好きになってしまうような女の子ってこんな感じなのかな。最後の余韻は悪くない。

函館出身の作家佐藤泰志の芥川賞候補作品「きみの鳥はうたえる」の映画化である。原作は未読。海炭市叙景、そこのみにて光輝く、オーバー・フェンスと佐藤泰志原作の映画化作品はいずれも傑作であった。函館の町を舞台に社会の底辺をさまよう人たちに存在感を持たせる。今回も期待して映画館に向かう。
結果としては、前の3作ほど良くはなかった。でも、この映画でも若い3人の若者が函館の街に放たれている。寂れつつも独特の存在感を持つ函館の街の匂いが映画全面に漂う。クラブやビリヤード場の映像は今までの作品になかったところ、猥雑で喧噪な若者のたまり場に流れる雰囲気はいい感じだ。函館山や路面電車を3人のバックの映像にチラチラ登場させるのを見ると、直近に三度函館で遊んだ自分はなんかわくわくしてしまう。
調べると、この題ってビートルズの「And your bird can sing 」の日本語訳ですってね。アルバム「リヴォルバー」の中にあるジョン・レノンの曲、ジョンとジョージのツインギターで軽快に始まるジョン・レノンのヴォーカルが印象的な自分の好きな曲だけど、映画の中じゃ全然流れなかったなあ。全く気づかなかった。
函館郊外の書店で働く「僕」(柄本佑)は、失業中の静雄(染谷将太)と小さなアパートで共同生活を送っていた。ある日、「僕」は同じ書店で働く佐知子(石橋静河)とふとしたきっかけで関係をもつ。彼女は店長の島田(萩原聖人)とも抜き差しならない関係にあるようだが、その日から、毎晩のようにアパートへ遊びに来るようになる。こうして、「僕」、佐知子、静雄の気ままな生活が始まった。

夏の間、3人は、毎晩のように酒を飲み、クラブへ出かけ、ビリヤードをする。佐知子と恋人同士のようにふるまいながら、お互いを束縛せず、静雄とふたりで出かけることを勧める「僕」。
そんなひと夏が終わろうとしている頃、みんなでキャンプに行くことを提案する静雄。しかし「僕」は、その誘いを断り、キャンプには静雄と佐知子のふたりで行くことになる。次第に気持ちが近づく静雄と佐知子。函館でじっと暑さに耐える「僕」。3人の幸福な日々も終わりの気配を見せていた……。 (作品情報引用)

アパートで同居する男2人に女の子が絡まる函館が舞台の青春映画、僕と佐知子が何気ないきっかけでぐっと近づいていく。2人が働く本屋の店長と付き合っていたのに、佐知子は気がつくと若い僕との付き合いが楽しくなる。僕の同居人の静雄も加えて夜通し遊んでいくうちに静雄にも情が移る。三角関係になるわけだ。でも、激しい葛藤があるわけではない。淡々とストーリーが流れる。起伏の少なさが若干物足りない。
石橋静河がいい。石橋凌と原田美枝子の娘と聞くと驚くが、何となく面影はある。かわいい。ここでは柄本佑と軽い絡みを見せるが、バストトップは見せない。若くして大胆に脱いだお母さんとは違うなあ。母娘バストの形は似るというが、24歳だからかまだ出し惜しみだ。

クラブのシーンでは、ソロで踊ったりする。うまいというわけではないが、まあ味のあるダンスを踊っていると思ってプロフィルを見たら、一応はダンサーという肩書きもあるんだね。萩原聖人演じる中年の店長と不倫関係にあるという設定だけど、不自然さがない。大人びている。親も親なんでませた人生送ってきたんだろう。この若い2人がともに好きになってしまうような女の子ってこんな感じなのかな。最後の余韻は悪くない。